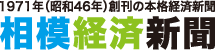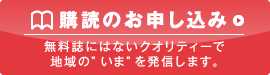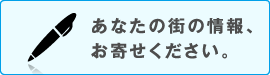製造業・中小企業
-
海老名商工会議所はこのほど、動画配信サイト・ユーチューブに会員事業所を紹介するチャンネル「えびな商工フェアCHANNEL(チャンネル)」を開設した。製造業や飲食店、美容室などを中心に30事業者が参加している。市内事業者を広く周知することで、海老名全体のにぎわいを創出したい考え。【2022年2月10
-
相模原・厚木・座間・海老名の4市と愛川町、清川村の首長らが相模川流域の共通課題について話し合う「県央相模川サミット」(会長=小林常良・厚木市長)はこのほど、オンラインで会合を開いた。大規模化・広域化する水害への対策や、県央地域を中心に広がっている「ナラ枯れ」被害について意見を交換。新型コロナウイルス
-
相模原市から東京2020五輪・パラリンピック競技大会の組織委員会に無償で提供した「津久井産木材」が、公共施設の家具などとして順次利用を開始されている。選手村ビレッジプラザに使われ大会終了後に返却される木材の活用方法として、五輪の記録を将来に伝えるとともに、地産材の魅力をアピールしようと検討していた。
-
相模女子大学(相模原市南区文京2)は、愛知県内の民間企業と共同研究で「名古屋コーチン味噌煮」を開発し、1月18日に宇宙航空研究開発機構(JAXA)から「宇宙日本食」としての認証を取得した。東海地方の食材を使い、食やかみ応えを残し、宇宙空間でのストレス軽減を目指したことが特徴。JAXAが管理する国際宇
-
さがみはらロボットビジネス協議会(SRB、事務局=相模原商工会議所)は、2019年12月18日~21日まで開かれた「2019国際ロボット展」に市内企業8社の共同ブースを出展した。産業用ロボットの実機を実演展示し、来場者からの注目を集めていた。相模原市も隣に出展し、関連企業などを紹介していた。 共同ブ
-
県はこのほど、企業誘致推進方策「セレクト神奈川100」で、県外企業による相模原市内への投資計画など4件を認定した。このうち3社を「輸送用機械器具関連産業」として選び、企業誘致を促すための融資、税制措置で支援する。 航空機用部品加工や高圧コントローラーバルブ製造などを手掛ける「三差製作所」(横浜市都筑
-
相模原市はこのほど、2020年度予算の編成方針を明らかにした。行政サービスの現行水準も維持できないため、新規・拡充事業の停止や今後本格化する大規模な事業を一時凍結する。20年から27年までの長期財政収支について仮試算を行ったところ、約60億〜約134億円の歳出超過が見込まれる。 財政の状況は、少子高
-
相模原市など全国20政令指定都市の首長で構成する指定都市長会(会長・林文子横浜市長)は11月18日、東京都中央区で会合を開いた。相模原の本村賢太郎市長らが4つの提言・要請を取りまとめ、「公共施設等の長寿命化」「医療提供体制の確保」などを各分野の担当大臣に提出する。 さいたま市長は、地価や物価が相対的
-
三菱重工グループの三菱重工環境・化学エンジニアリング(MHIEC、横浜市西区)は、横浜市から一般廃棄物焼却施設「資源循環局鶴見工場」(鶴見区末広町)の焼却炉等改修工事を受注した。処理能力1日当たり1200トンのストーカ式焼却炉設備を改修し、長寿命・省エネルギー化を図る。受注額は61億2700万円(税
-
さがみ湖リゾートプレジャーフォレストを運営する相模湖リゾート(相模原市緑区若柳)と富士急行、SB(ソフトバンク)ドライブは11月25日、園内で自律走行バスの実証実験を報道関係者などに公開し、試乗会を行った。無人で運行するシャトルバスとしての導入を目指しており、自律走行バスの技術や車両内の乗客数を検知