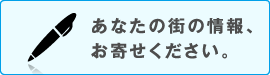市内初となる個展を開いた遠藤彰子さん(68)は、相模原市南区西大沼にアトリエを構え47年間、近年は500号~1500号の大作を中心に描く。安井賞や文部科学大臣賞などの栄誉ある賞を受賞したほか、2014年に女性美術家として初の紫綬褒章を受章。武蔵野美術大学油絵学科の教鞭を取り、明日の芸術界を支える若き美術家の育成に尽力している。この夏、市内で初めての個展を開き、「美術館整備など市内の文化隆盛の機運が高まれば」と期待する。大草原のように広大な精神世界を駆け抜け、好奇心の旺盛さと美への探究心は尽きることがない。
(芹澤 康成/2016年8月10日号掲載)
■相模原で活動へ
遠藤さんは1947年、東京都中野区のごく一般的なサラリーマンの家庭に生まれた。幼少期から絵を書くことが好きで、舗装されたばかりの道路にろう石で自分や友達の顔を描いていた。
画家への憧れを叶えるため、都立駒場高校芸術科、武蔵野美術短期大学へと進学した。大学で油絵や彫刻、陶芸などを学び、本格的に洋画家への道へ進もうと決意する。
結婚を機に、21歳でまだ多くの自然が残っていた相模原に移住。アトリエ兼住居を現在の西大沼に構え、絵画教室で生計を立てながら本格的に創作活動を開始した。
当時の様子について「東側にはツタが絡まった木のある雑木林が広がり、野ウサギやヤマバトがいた。国道16号から自宅まで畑で、目印として屋根に描いた猫の絵が見えた」と振り返る。
遠藤さんは、散歩をしていた「こもれびの森(相模原中央緑地)」で、緑と動物の豊かさにインスピレーションを受け、生まれたのが「楽園」シリーズだ。
長男が生後8カ月で、腸の一部が腸自体に入り込んでしまう「腸重積」にかかり、生死の間をさまよった。奇跡的に手術は成功し、一命を取り留めた。このできごとは、遠藤さんに「平和な日常生活が、呆気なく崩れ去ってしまう」と衝撃を受けさせた。
「楽園は甘いのではないか」と悟り、「街」シリーズを描くようになる。オランダの版画家エッシャーのだまし絵のようで、街の景色に一歩足を踏み外せば地に落ちる「危うさ」を感じる。
■安井賞を受賞
遠藤さんは、第29回安井賞展(86年)に街シリーズの集大成『遠い日』を出展。新人洋画家の登竜門とされ、画壇の芥川賞とも称される「安井賞」を受賞した。
同賞受賞を機に武蔵野美術大学油絵学科の講師に招かれる。96年に助教授(当時)に就任し、99年から教授を務める。かつての教え子の呼び掛けで、アトリエに教え子が集まってクリスマスパーティが開かれるほど。
「若手の美術家にとって人脈作りは重要。40代のOB・OGが来れば、現役の学生も集まり、よい交流の場となっている」と遠藤さん。
遠藤さんは15年、仏・パリ国立高等美術学校(エコール・デ・ボザール)の依頼で、招へい教授として授業や講演会、作品展示を行った。14年に上野の森美術館で開催された個展の副題に合わせ、「魂の深淵をひらく」というテーマで、音楽やダンス、哲学、絵画組成、美術鑑賞などのカリキュラムが組まれた。
「フランス人は質問が的確で、ディスカッション能力の高さには驚かされた。ボザールの先生方や学生たちと触れ合えたことで、日本とは異なるアートという概念や考え方の違いを肌で感じることができ、とても大きな刺激を受けた」と振り返る。
■広大な精神描く
『みつめる空』(1989年、市所蔵)に始まる大作シリーズは、500号(248㌢×333㌢)をひとつの単位とし、遠藤さんの精神世界の壮大さを物語る。生と死、光と闇、創世と破壊が神話のように普遍的、根源的な奔流となって表現される。
8月6日から28日まで市民ギャラリーで市内初となる個展「遠藤彰子の世界展~COSMOS~」を開いている。500号から1500号の大作のほか、立体作品や幼少期の作品など貴重な作品も展示した。
個展のために描き上げた100号の新作『眸(まな)ひらく明日』は、フランスで見た騎馬劇団「ジンガロ」の公演がモチーフ。「数十頭の馬が丸い舞台の上を駆け回る躍動感が、生命の象徴のように見えた。馬と人間が絡み合うような世界を描いてみたいと思った」と話す。
創作する作品は洋画だけではない。幼い頃から好きな猫を象った彫刻や自身の作品『黄昏の笛は鳴る』(91年)などを収めた額、さらに普段身につけるアクセサリーも手がける。
新しい試みも欠かさない。『HORIZON』(95年)は「洛中洛外図屏風のように煌びやかな絵が描きたい」と日本画の要素を取り入れ、金箔を使った。「失敗だったが、学ぶこともあった。金箔の色が強い。大和絵にふさわしい色の使い方がある」と前向き。
遠藤さんは「これから70代、80代と歳をとっていくが、その時々の感性で絵を描くことが楽しみ。歳を取った自分がどうなるか、未知のものへの楽しみがある」と、創作意欲は色あせない。