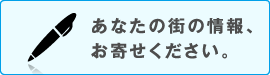相模原生まれで相模原育ち。寿司職人を志して東京で過ごした7年間の修業時代以外は、58歳の今までずっと故郷で暮らしている佐藤茂さん。33年続く藤寿司(中央区富士見)の創業者だ。「相模原の土地も人間も大好きだ」と活気あふれる声で愛着を語るが、それだからこその心配も隠さない。「ネタを仕入れる市場が寂しくなってしまった。相模原の食を守るためにも、市や商工会議所などに相模原綜合卸売市場存続へのテコ入れを期待している」と胸の内を明かす。
(編集委員・戸塚忠良/2016年9月1日号掲載)
■25歳で開業
富士見に生まれた佐藤さんは道一本隔てた中央小を卒業後、開校したばかりの清新中に1期生として入学。小学生のときから好きだった野球部に入り、先輩がいないなかで、3年間キャプテンを任された。守備は捕手。1年生秋の市大会で準優勝を飾って母校に初めての表彰状をもたらしたのは忘れられない思い出だ。
横浜商大付属高校に進んでからも主力キャッチャーとして活躍。県大会でベスト8に進んだのが最高成績だった。
卒業時には野球で誘ってくれた大学もあったが、自分で決めた進路があった。「当時テレビで『拝啓おふくろ様』という連続ドラマをやっていて、萩原健一が演じる板前のかっこよさに憧れた」という。
こうして卒業後、親戚の紹介で東京・青山大寿司総本店の大前錦次郎さんに弟子入りし、寿司職人の道を歩み始めた。全国すし連合会の会長も務めた大前さんは、「寿司を世界に広めた」と評される先覚者。
朝5時から夜中まで及ぶ板前修業は厳しく、「特に最初の冬、水仕事でひび割れした手がひどく痛むのがつらかった」という。それでも、「同じ時期に就職した4、5人の仲間と一緒だったから楽しいことも多かった」。そのころ書き留めたノートは今でも大事にして手元に置いている。
7年経ったころ大阪へ腕だめしをしに行こうと思ったが、不動産業を営んでいた父親が土地と店舗を用意してくれたため、父親の会社の商号をとった藤寿司を開店した。25歳の若い職人経営者の誕生である。
■地元に添った商売
「東京で習ったことを全部出そうという気持ちだった」が、にぎわいにあふれる都会の人たちの需要と、「店のまわりには何も無かった」という環境の中で、開店した藤寿司への需要は同じではなかった。
「同じ刺身の盛り合わせを出しても、東京なら『なかなかきれいだな』という反応があるのに、ここでは『値段が高そうだな』という声が返って来た」と、当時のありのままを語る。
「相模原での商売の仕方を考えなければだめだ」と感じ、値段を安く抑える工夫を重ね、一期一会の気持ちで客に接することを肝に銘じた。
親戚や旧知の人たちが足を運んでくれるうち、市役所や近くにできた県合同庁舎などのなじみ客が増え、40人ほどの宴会にも使われるようになった。「競合する店も少なくて、いい時代だった」と表情を和らげながら振り返る。しばらくしてPRの意味合いを込めたランチも始めた。一緒に店を支える妻の浩子さんとは幼なじみの間柄だ。
■野球という絆
野球好きは今でも変わらず、選手の色紙を飾っているうち、同好の客が有名プレーヤーの色紙やサインボールを持ち寄ってくれるようになった。さらにアマチュア野球の監督らがチーム名入りのボールを寄付してくれるようになり、店内に数十個を収めた展示スペースを置いている。
「今は野球好きの人たちのたまり場のようになっていて、店を閉めた後プロアマを問わずいろいろな野球の話をするのが楽しみ」と佐藤さん。
夜は年配客が多く、一品料理が好評。ランチには若いサラリーマンや女性客が気軽に足を運んでいる。お得感のあるにぎりやバラチラシはもちろんだが、毎週一度のうなぎランチも人気の的。「夏の土用の丑の日にやったら大好評で、ランチメニューに加えた。千円というのはギリギリの価格。仕入れ先の業者にも泣いてもらっている」と笑う。
■市場振興の願い
日頃の仕入れで特にこだわっているのはマグロ。その中でも「一番うまいのはコレ」と太鼓判を押すクロマグロの品定めには目を光らせる。
東淵野辺の相模原綜合卸売市場で仕入れるが、その市場は老朽化が著しく、鮮魚店は一店のみ。
「市場に活気がないと品物が限られて取り合いになり、自分が欲しいものを仕入れるのが難しくなる。値段の駆け引きにも力が入らない」と苦い顔。「市が新しい施設を作ってくれればと願っている。商工会議所にも頑張ってほしいね」と繰り返し力説する。
この道40年。師匠に言われた「仕事場はお前が生きる舞台」という言葉を忘れず、自分の腕と心通う会話、そして妻浩子さんとのあうんの呼吸の接客で、愛着深い地元に密着した営業を続ける。