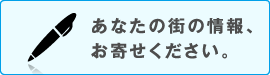瀬戸内海の豊島出身の小林さん
東日本大震災による原発事故発生後間もない時期の福島県内の姿を伝える写真展が4月15日まで、相模原市中央区富士見の市立環境情報センターで開催されている。写真家・小林惠さん(68)のモノクロ作品約七十点を集めた「風景色 フクシマノート」と題する作品展だ。発生後の2011年6月から一年余りにわたり立ち入り禁止区域ぎりぎりまで足を運んで人跡まれな地域の風景を写しとった一枚一枚は、原発事故によって何が失われ、何が残ったかを静かに語りかけている。(編集委員・戸塚忠良/2017年4月1日号掲載)
■写真家の道
小林さんは香川県・豊島(てしま)生まれ。高校卒業後、日本写真専門学校で学んだ。「もともと映画作りに興味があったが、リアリズムを柱にした写真雑誌を見て魅力を感じ、写真を勉強したいと考えるようになった」という。写真家の棚橋紫水氏の教室にも通って技術と知識を深めた。
社会の現実を見つめ、その本質をえぐり出すリアリズムへの執着は途切れることなく今につながっている。
学校卒業後は広告代理店や福祉施設での勤務を経て、フリーとして独立。40年ほど前から座間市に住んで、さまざまな写真展に参加する一方、企業パンフレットやチラシなどを手がけるようになった。
実績を積み上げるなかで、相模原市内在住で日本を代表する写真家の一人、江成常夫氏の厚誼を受けたのをはじめ、さまざまな分野のライターと知り合い、仕事の幅も広がっていく。
今は都内、県内自治体の広報紙や写真講座などに携わっており、公益財団法人日本離島センターの広報季刊誌『しま』にも作品を寄せている。
■福島との出会い
2011年3月11日の東日本大震災に強い衝撃を受けた小林さんは1カ月後から東北へ数回足を運び、宮古、石巻、三陸の島々を見て回り自然の脅威を心に刻んだ。
しかし、その帰り道、福島県内各地で人の気配のない荒涼とした風景や営業を中断したコンビニ、機動隊の駐屯地と化した公民館などを目のあたりにするうち、「しっかり見るべきはフクシマだ」という思いが強くなった。
その後すぐに放射線計量器を購入して毎月一回、飯舘村、浪江町、川内村などの情景をカメラに収め地域の再生がどう進んでいくかを見守った。人の立ち入りが禁止されている警戒区域のゲートぎりぎりまで迫って撮影することもしばしばで、時には区域内にまで足を踏み入れて係員から許可証の提示を求められることもあった。
目に映る情景は、主が立ち退いた家屋、人無き里の神社や祠(ほこら)、放射能の除染作業、校庭が汚染物質の仮置き場になった学校など、原発事故の影響を示すものばかり。
「道を這う蛇を撮ったときには、この蛇さえ被爆したかとを思うと哀れを感じざるをえなかった。『蛇の涙』というタイトルを付けようと思った。物言わぬ草木に対しても同じ哀れを感じる」と顔を曇らせながら語る。
その一方、被爆した飼牛の殺処分を拒否して災禍を乗り越えようと奮闘している「希望の牧場」では、人々の強い精神力に心を動かされた。
■復興を祈って
国による避難指示区域の除染作業は完了したとされるが、帰還困難区域の除染と住民の帰宅に向けた環境整備にはなお長い道のりが残されている。被災地の復興と原発の今後を小林さんはどう展望するのだろうか。
「廃炉作業を進めて元の通りにすればいいというものではないと思う。住民一人ひとりの穏やかな暮らしが突然断ち切られて、先が見えない状態になってしまったことのメンタルな損失は計り知れない」と語気を強め、「経済的にも火力発電のコストに比べて、原発事故の処理にかかる費用は膨大な額に上るはず」と、原発の存在に強い疑問を投げかける。
そして、発生後6年経って事故の記憶が風化することを危惧して、「フクシマを忘れるな! まだ何も終わっていない」と警鐘を鳴らす。
■2つの写真展
実は、「風景色」展と時を同じくして、東京・銀座のニコンサロンで「潮路の譜」と題する小林さんの写真展が開かれている。日本最南端の離島群の過去と現在の断片を発信する個展だ。
戦争と社会の変化によって移り変わる島々の姿を写し取った作品を解説する中で、小林さんは「島の精神は継承されている」とコメントしている。
風が吹きぬける被災地の光景はふるさとを失った人々の悲しみを語り、黒潮洗う離島の情景はふるさとに生き続ける人々の精神のたくましさを告げる。それらに通底するのは、現実と向き合い苦難や困難を乗り越えようとしている人々への深い共感に違いない。