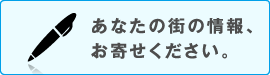今や日常生活で欠かすことのできない素材、プラスチック。相模原市中央区東淵野辺に、業界から注目される町工場がある。その会社は「日本油機」。創業者である市川十四男会長は現在87歳。プラスチック成形の分野に携わって半世紀以上。成形機の基幹部品の設計、製作などを手掛ける。今でもひたすら図面に向かう。ただ、ここまでの道のりは決して平たんではなかった。若くして立ち上げた企業は、一度は大手企業の波にのまれ倒産。挫折からの再出発を誓い、オンリーワン企業へと導いた。(千葉 龍太)
今や日常生活で欠かすことのできない素材、プラスチック。相模原市中央区東淵野辺に、業界から注目される町工場がある。その会社は「日本油機」。創業者である市川十四男会長は現在87歳。プラスチック成形の分野に携わって半世紀以上。成形機の基幹部品の設計、製作などを手掛ける。今でもひたすら図面に向かう。ただ、ここまでの道のりは決して平たんではなかった。若くして立ち上げた企業は、一度は大手企業の波にのまれ倒産。挫折からの再出発を誓い、オンリーワン企業へと導いた。(千葉 龍太)
■第3の物質
? 家電や日用品、自動車など、あらゆる製品に使われているプラスチック。成形するには、「射出成形機」の存在が欠かせない。原料となる樹脂ペレットを溶かしながら、金型に送って、製品に仕上げる装置だ。
創業以来、日本油機手掛けるのは、こうした成形の技術だ。
市川会長の人生は、「プラスチック一筋」と言っても過言ではない。大正14年生まれ。太平洋戦争中に出征し、終戦後に東大阪の町工場に旋盤工として就職した。それから数年後、その後の人生を変える〝出会い〟があった。
「この機械を修理してくれないか」。取引先から回ってきた装置は、当時では珍しかったプラスチックの成形機だった。
戦後まもない時代。市川会長は、プラスチックの存在を知ることになる。今でこそ当たり前のプラスチックだが、当時は「第3の物質」とも呼ばれ、貴重だった。
仕事で接している金属とも違う。おまけに軽い。いつかこの素材が当たり前になる時代が来るのでは。そう感じた市川会長。プラスチックにすっかりと魅了される。28歳で独立を果たした。
市川会長の「大阪成形」は、東大阪で産声を上げた。借家を工場に改装し、たった一人での創業だった。業務内容はプラスチック成形機の開発と製造。ところが、最初からノウハウがある訳ではない。「他の装置を仕入れてきて、見よう見まねで作り、覚えていった」と、振り返る。
■倒産の経験
始めは順調だったものの、「プラスチック時代の到来」を予感したのは、市川会長だけでなかった。やがて、大手企業が続々と参入。気づけば市川会長の仕事は激減。「大阪成形」の存続を断念することになった。1963年のことだった。
「会社はつぶれても、命までは奪われることはない。また再起できる。敗者復活だ」と自分自身に言い聞かせた。
プラスチック成形機の製造分野では、大手企業とは張り合えないことは、痛感した。では、何ができるのか。
着目したのは、成形機の中核部品となる「スクリュー」の設計だった。自動車に例えるなら、スクリューは成形機の「エンジン」にあたる。スクリューに問題があれば、決して質の高いプラスチック製品は作れない。不良の原因にもなる。市川会長ならではの着眼点だった。
1987年に「日本油機工業」を設立。再出発を始めた。
■相模原移転
やがて取引先は関東にも広がる。そのなかで、腕を見込んだ相模原の同業者から、声を掛けられ1980年、同社と合併することになる。拠点も東大阪から相模原へと移った。
とはいえ、一本一本のスクリューを丁寧に製作しようとする市川会長。それに対し、下請け企業体質で、量産品を重視する合併先の相手。水と油だった。
「世の中には、どうしても大量生産しないものもある。それらを作るには、オーダーメードのスクリューも必要になってくる」
今でこそ、少量多品種で付加価値を付けるのは、中小企業にとっても自然な話だが、当時では、早すぎる考えだった。結局、会社を去ることになり、1987年に「日本油機」を設立した。それが現在の会社である。
ただ、当初は、妻・美代子さん(現・日本油機専務)と息子の3人しかいない小さな町工場に過ぎない。
開発に集中する職人気質の市川会長の傍らで、美代子さんは営業や経理など、事務仕事をこなし、夫を支えていく。今の日本油機があるのは、市川会長の力はもちろんだが、美代子さんの存在も大きいともいえる。
■情熱消えず
現在、日本油機が手掛けるのは成形機のスクリューの設計だけではない。工場内で廃材になったプラスチックを、現場で再原料化できる装置「バンビ」も開発。欧州やアジアなど世界10カ国以上に輸出する、れっきとした〝メーカー〟にもなった。気づけば社員も15人に増えていた。
「成形機のスクリューについて知り尽くしているのは、日本では自分しかいないだろう。その意味は、最後の職人かもしれない」と話す。一線を引いた今でも、技術者として、そして職人として、モノづくりの現場に立つ。
戦後の焼け野原から始まった市川会長のプラスチックに賭けた人生。戦後の経済成長と「メイド・イン・ジャパン」を支え続けてきた情熱は、決して消えることはない。
今、その精神は、若い社員たちに受け継がれている。