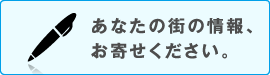〝脱下請け〟を模索する市内の中小企業にとって、おそらく、この会社の存在を知らない経営者はいないだろう。環境装置メーカー、共立(相模原市緑区西橋本)だ。一介の町工場だった同社が、自社ブランドの製品を立ち上げて10年余り。今や「ごみ分別機」の中・大型機のシェアは国内トップになるまでに成長した。経営の舵(かじ)を取るのは女性社長。病で倒れた父親から、会社の経営を託されるまで、普通の主婦だったという。父の会社を残したい―。家族愛と親孝行の気持ちが、数々の苦難を克服する糧になった。 (千葉 龍太)
■主婦から転身
上野賢美社長が率いる共立の本社があるのは、数多くのベンチャー企業が入居するインキュベーション施設、さがみはら産業創造センター(SIC)内。〝ベンチャー企業〟といっても、同社の歴史は古い。設立は1956年になる。
前身の会社名は「共立工業」。化学プラント向けの真空容器や遠心分離器などを手掛け、大手メーカーに納める完全な〝下請け企業〟だった。
当時は、どこの大手企業も、国内生産を主力としてきた。下請け企業にとっても、営業をしなくても、大手からの受注が次々と舞い込んでくる良き時代だった。
そんな同社に転機が訪れたのは95年のこと。父親の先代社長が病で倒れ入院した。中小企業にとって、経営者の不在は、存続危機を意味する。
そこで、都内で主婦をしていた長女・上野社長が、急遽、経営を託された。上野社長は振り返る。
「最初は父が退院までの約束でした。正直、会社でどんな仕事をしていたのかも分かりませんでした」
■第二の創業を
ところが、間もなく時代の流れに巻き込まれる。急速な円高だ。当時も昨年の〝超円高〟と同様、1ドル=80円割れを記録したほど
円高不況により、発注元の大手メーカーは、生産拠点を相次ぎ海外に移管していく。それは、下請け企業にとって、受注減につながった。
このままでは会社の存続が危ぶまれる。一時期は、海外進出も検討したが、資金的に余裕がなく、リスクも大きい。
決断したのが「自社製品を開発して第二の創業を目指すこと」だった。
そこで目を付けたのが、環境分野。ニッチな環境装置なら自社の技術を生かせ、市場ニーズもあると判断したからだ。
最初は父の復帰までの間と決めていた上野社長も、いつしか、経営者として腹を据えるようになっていった。
当初は苦難の連続だったという。「生ごみ乾燥機」の開発では、食品残渣(ざんさ)をミキサーにかけ、フライパンで火になるまであぶったこともあった。
さらに、ようやく完成させた装置も、設計どおりに稼働しないことも多々あった。
「父の生きている間に会社を残したい」 苦労が重なる中でも、そんな思いが上野社長を支えていた。
■国内トップに
こうして2000年に第1段の自社製品「ごみ分別機」を発売。その後は製品のラインアップも次々に増やしていった。
今やごみ減量化やリサイクルは自治体にとっても必須の課題。
やがて装置も次第に認知されるようになり、今では「中・大型分別機」と呼ばれる分野でトップシェアを持つ企業となった。
会社の売上高は経営を引き継いだ当初の5億円から15億円(12年度)に。自社製品の製造販売事業の売上高構成比率も、主力の環境事業でほぼ100%を占めるようになった。
従業員数は、グループ全体で約60人になり、もはや〝ベンチャー〟でもなくなった。現在は海外市場での販路拡大を狙っている。
■製品の展示場
上野社長は、自社製品が市場に受け入れられた要因として〝自社製品の展示場づくり〟を一番に挙げる。
すでに納入したユーザーの現場を「展示場」にしてもらい、購入を検討している取引先を連れて行く。そして装置が稼働している様子を実際に見てもらう。
どんなに営業トークが上手でも、「装置は順調に稼働するのか」という顧客の不安までは拭い切れない。
まさしく、〝百聞は一見にしかず〟なのだ。現在でも、月に2~3回は、展示場へと招待している。
会社や製品のブランド力を高めることにも力を注いだ。
といっても、大手企業のように、多額の広告宣伝費を使うのではなく、納入後のアフターサービスも徹底させた。採算は度外視しても、顧客が納得するまで向き合ったという。
「ブランド力は、一朝一夕では築けません。ブランド力イコール信用力なんです。こうした積み重ねることが重要です」と繰り返し説く。
主婦から経営者に転身し、共立を成長させていった上野社長。
これまで数々の苦難を重ねながらも、全くそれを感じさせないほど、上野社長は明るい人柄だった。きっと、会社を動かす原動力にもなっているに違いない。