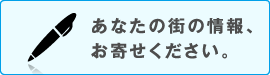相模湖(相模原市緑区)近くの若柳で、世界トップクラスの辛さを持つ唐辛子が栽培・生産されていることをご存じだろうか―。ギネス記録で世界一辛いと認定された唐辛子「ブット(ブート)・ジョロキア」の加工に初めて成功した竹内僚さん(40)=七海交易代表=。現在こそ大手加工食品メーカーや外食チェーンなどとの取引があるが、鮮やかに赤い〝悪魔の実〟の呪いは一筋縄では行かなかった。【2020年9月20日号】
相模湖(相模原市緑区)近くの若柳で、世界トップクラスの辛さを持つ唐辛子が栽培・生産されていることをご存じだろうか―。ギネス記録で世界一辛いと認定された唐辛子「ブット(ブート)・ジョロキア」の加工に初めて成功した竹内僚さん(40)=七海交易代表=。現在こそ大手加工食品メーカーや外食チェーンなどとの取引があるが、鮮やかに赤い〝悪魔の実〟の呪いは一筋縄では行かなかった。【2020年9月20日号】
※全文はnote(https://note.com/sagamikeizai/n/n5c3146e1ea33)でもお読みいただけます。