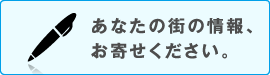22年の新作「山鳴りひびく」の前で取材に応じる遠藤さん=2022年12月16日、本紙記者撮影
500号(248・5㌢×333・3㌢)を超える巨大画の存在感と、作品に込められた「人間の存在」や「生きている実感」といったテーマが織りなす深い物語性が、見る者を絵の世界に引き込もうとする―。相模原市南区在住の洋画家・遠藤彰子さんの個展「巡りゆく 遠藤彰子展」(主催・実行委員会=長野二紀会、上田市など)が、長野県内の上田市立美術館(天神3)で開かれている。本紙記者が足を運び現地の反響を取材したほか、コロナ禍でも精力的に活動の場を広げている遠藤さんの近況について話を聞くため相模原市内のアトリエも訪問した。(芹澤 康成)【2023年1月1日号掲載】
□壮大な作品目の前で

上田市副市長が出席したほか、経済、文化各界から来賓が招かれた式典=2022年12月16日、上田市立美術館
初日の2022年12月16日には、同美術館でオープニングセレモニーが開かれた。同市の吉澤猛副市長や佐藤論征市議会議長を始め、市関係者、美術団体・長野二紀会会員らが出席し、個展開催を盛大に祝った。観覧やスライドトークには同県内各地のほか、神奈川県からも多くのファンが駆けつけていた。
主催者を代表したあいさつで、吉澤副市長は「人間の存在や生命の循環をテーマに描いているが、壮大で迫力ある作品の世界を目で観るだけでなく、体感してもらいたい。子供や若い世代の人にさまざまなインスピレーションを喚起してもらい、地域をけん引していく個性と、感性豊かな次世代の育成につながっていくはず」と期待感を示した。
実行委員長で、米津福祐氏(長野二紀会会長)は、個展の開催について「市民にとってありがたいことで、実行委員会としてもワクワクしている。上田市内に限らず長野県中にファンがたくさんいる」と話す。遠藤さんの作品を「自身の日常の暮らしに密着し、懸け離れたモチーフ(描画対象)は登場しない。身の回りの写生、自身の体験に基づく描写はだれにも分かりやすく説得力を帯びている」と評した。
□上田市との交流40年
遠藤さんは1980年代前半に、同美術館の前身「山本鼎(かなえ)記念館」と信濃デッサン館を訪れたのが、初の同市訪問。「当時は名もない新人画家の1人で、山本鼎をはじめ色々な作家の作品を観て勉強していた」と振り返った。その数年後に上田創造館で、人生初の講演会を行うことに。「頭が真っ白になったが、農家の方からいただいたリンゴを食べて元気が出た」と明かす。
武蔵野美術大学教授(当時)として、同市などが主催する公募展「山本鼎版画大賞展」の審査員を99~2011年(第1~5回)の間務めたほか、14年に開館した同館収蔵美術作品・資料等の選定委員にも任命された。「版画には詳しくなかったが、審査しながら勉強になった。白と黒の制約の中で、世界をどのように構築していくかというおもしろさがあり、毎回審査するのが楽しみだった」と顔をほころばせた。
審査員や選定委員などとしての交流を通じて「長野には多くの絵描き仲間ができた」。同市初となる自身の個展開催を「若い頃から上田市とは縁が深かったが、私の作品を信州や上田の皆さんに観てもらえる初めての機会。気を引き締める機会にもなった」と喜び、「一歩一歩精進してがんばりたい」と今後の活動にも意欲を滲ませた。
50年を超える制作活動について初期から現代まで紹介し、制作順と年代で3部構成となっている。まず目を引くのは、会場に入ってすぐに展示された1500号(500号を3枚連結)の大作『鐘』(07~08年)だ。作品全体としては初公開となる最新作『山鳴りひびく』(1000号)など大作シリーズを中心に、相模原市所蔵の作品3点、新聞各紙に掲載した挿絵、立体作品など60点以上を展示している。

『山鳴りひびく』(2021年 油彩、キャンバス 333・3㌢×497㌢)画面を分断するように流れる黒い川は、新型コロナウイルス感染症やウクライナ危機など、社会を分断するような世界的な不安感を表している。「馬」は遠藤さんのほかの作品にも登場するが、「力強く美しい姿が子供の頃から気に入っている」と今作にも取り入れたという。
『山鳴りひびく』は、陰陽五行をテーマとした全5作のうちの「土」をイメージした作品であり、大樹が燃え盛る様子を表した『炎樹』(17年)の次の場面を描いたもの。「生命が終わりを迎え、大地へと還っていき、乾いた音が山に鳴りひびくさまを表した」と説明する。シリーズを通して「世の中のすべてのものは移り変わり、生まれては消えていく運命を繰り返し、永遠に変わらないものはない」ということを表現している。
遠藤さんは、現地での取材に「1人で細々と描いていても元気がでない。実際に絵を見てもらえることで勇気が出るし、先々でのさまざまな反響の声がモチベーションになる」と答える。長野の自然などで制作の参考になったものについて尋ねると、「今すぐ(イメージが)わくものではないが、今後の作品にリンゴが登場するかも。空や雲の壮大さは相模原や東京では感じられない」と語った。
個展は2月12日まで。会期中、休みは今月3日までと火曜日。開館時間は午前9時~午後5時。