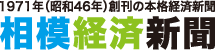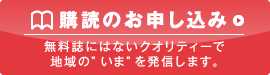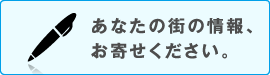県中小企業家同友会(神奈川同友会)は1月31日、市立産業会館(相模原市中央区中央3)で地域と企業が障害の有無に関わらず「ともに育ち輝く」方法・実践を考えようと、雇用創造フォーラム「みかさんイン相模原」を開いた。会員の経営者や社員のほか、障害者福祉行政、福祉法人、教育機関の関係者らも参加した。【2025年2月10日号掲載】

神奈川同友会相模原支部支部長で実行委員長の本庄浩義さん(ミナシアホールディングス会長)は「相模原でも少子高齢化、産業構造の変化などに伴い雇用問題は深刻化していくはず。多様性を生かす視点を取り入れることで、新たな雇用を生み出す大きなチャンスに変わる。多様な働き方や雇用について考え、地域課題を解決する糸口を探る機会としてもらえれば」と話した。
民間企業に雇用されている障害者は、法定雇用率(2・5%、40人に1人)の引き上げに伴い年々増加している。厚生労働省の集計結果によると、2023年には全国で約68万人と前年比で5・5%増え、過去最高を記録した。しかし、法定雇用率未達成率は約6万社、うち障害者を1人も雇用していない企業は約4万社になる。
神奈川同友会は「法定雇用が義務付けられていない規模の企業では、障碍者雇用を検討したこともないところ(企業)も多くあると考えられる」と推測。働く意思や能力があるにも関わらず機会を逸している人たちの存在の一方、中小企業の人手不足を指摘した上で「障害のある人の活躍の場づくりは新たな人材獲得にもつながる、急務の取り組み」とする。
今回で2回目となる同フォーラムは「障害者雇用の可能性について、具体的な取り組みの方法を企業、当事者、社会全体に周知していく必要がある」との考えから、「みんなかつやくするカラフルかながわ」(「み」と3つの「か」で「みかさん」)を合言葉に立ち上げた。
沖縄の同友会が毎年開催している「雇用・就労支援フォーラム」をモデルに、神奈川同友会のダイバーシティ委員会が中心にとなって関係機関も参加する実行委員会を立ち上げ、2024年に小田原で初めて開催。県内10支部が持ち回りで開催しており、今回は相模原支部(相模原市内3区)が担当となった。
1部の基調講演では横浜市立大国際教養学部の影山摩子弥教授が「多様な人材の戦略的雇用」をテーマに語った。障害者雇用の成功事例を紹介し、職場全体のイノベーションやリスクマネジメントを促し経営改善につながるまでのメカニズムを説明した。
影山教授は、日本の国際競争力低迷の原因について「親のしつけや学校教育の影響で健常者は何が望まれ、正解が何かしか考えず、発想や言動が画一化している。多様性が縮減した健常者の発想ではイノベーションは生まれない」と指摘する。
雇用の際には、作業の単純化、個々の能力や特性に合わせた育成、分かりやすい作業環境の整備など「障害者に合わせた工夫が大事」とする。健常者も作業手順が分かりやすくなることで生産性が向上した例や、安全意識が向上することで労働災害の減少につながることもあるという。
2部ではさまざまな立場の人が垣根を越えて知る・つながるきっかけを作ったり、情報を共有したりできるようにと、3会場に分かれて3つの分科会を開いた。高齢者・外国人・障害者の雇用などに取り組む栄和産業、司法試験の音声受験(音声認識ソフトを使った受験)で日本初の合格者となった菅原崇弁護士、障害者雇用などで成功した事例を紹介した神奈川労働局とハローワーク厚木の専門家が先行事例を紹介した。