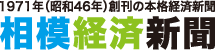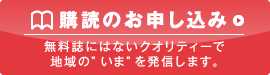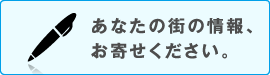宮ケ瀬ダム(愛川町半原)の堤体内で地域産のチーズなどを保管し、熟成する取り組みが2月28日から始まった。ダム近くの服部牧場のチーズ20㌔と、宮ケ瀬振興財団が用意したコーヒー豆(ケニア産)30㌔を3カ月、半年、1年などの期間で熟成させ、味や品質などを確認しながら定期的に頒布・販売する。今後、保管する食材を相模原市緑区や厚木市などの産品にも拡大し、ダム周辺地域の活性化を目指したい考えだ。【2025年3月10日号掲載】

同財団の仲谷政二郎理事長は「蔵出しをした後には地域の飲食店で地域の食材として提供してもらい、来店者にも味わって楽しんでもらえれば。さらに地元の土産としてブランド力を強化して、地域の観光作りに役立てれば」と期待する。
取り組みは、河川敷地を民間事業者などが営利活動に利用できるようにする占用許可制度「河川空間のオープン化」の一環。宮ケ瀬ダムの堤体とその周辺を都市・地域再生等利用区域に指定し、財団が許可を受けてダムの利活用を図っている。
宮ケ瀬ダムとその周辺の産品を活用して、新たなブランドの開発やダム集辺地域の観光活性化につなげようと、宮ケ瀬ダム周辺振興財団や服部牧場、同ダムを管理する相模川水系広域ダム管理事務所が連携する。2024年春に同牧場でチーズの生産にめどが立ったことを機に、北海道・札内川ダムの取り組みを視察した。宮ケ瀬ダムでもチーズなどの熟成保管ができないか試すことになった。
同ダムでは、19年から黄金井酒造(厚木市七沢)、21年から久保田酒造(相模原市緑区根小屋)がそれぞれ製造する日本酒を保管している。国内の他のダムでも日本酒やワインなどの酒類、などの長期熟成など保管の実証実験を行う事例はあるが、「チーズやコーヒー豆は珍しい」(係長・下嶋岳志さん)。
コーヒー豆は札内川ダムの事例を参考に、真空パックの生豆を保管。一定の温度で保管するため「品質が安定し、味がまろやかになる」(下嶋さん)という。
堤頂(構造高156㍍)から約135㍍下(広場は約125㍍下)にある幅2㍍ほどの点検や観測などに用いる通路。年間を通して気温や湿度の変化が少なく、温度10度前後、湿度90%前後。これは偶然にも同牧場の熟成庫とほぼ同じ条件で、「チーズの熟成にとって最適な環境」(浅見さん)。
同ダム関係者によると、通路がある位置は堤体の幅が180㍍ほどあり、分厚いコンクーリートの壁で日光や外気の影響を直接受けにくい環境。津久井地域などで震度4の地震があっても、ダム付近では震度2という強固な地盤の上にあり、災害にも強いという利点もある。

同日、同ダム管理事務所で式典が行われ、愛川町の小野澤豊町長のほか、同事務所、同財団、同牧場などの関係者らが出席した。
小野澤町長は「ダム貯蔵という付加価値を生かした商品開発を広めてもらうことに期待している。宮ケ瀬湖周辺地域の振興と活性化につなげていきたい」などと、今回の取り組みに期待を込める。
同牧場の服部誠会長(取材時点は社長)は「都市部に近い立地を生かし、〝ダムチーズ〟としてスペシャルなイメージで展開したい。乳脂肪検査では県内トップレベルの濃くておいしい牛乳で生産しているので、どんどん食べてもらえるのが楽しみ」と話した。