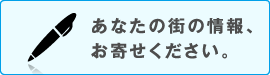焼き鳥、串カツ、おでん、団子…。どんな食材も串刺しにする自動串刺機市場で、国内市場シェア9割以上を独占する企業が相模原市中央区にある。社員数わずか5人のコジマ技研工業だ。同社の自動串挿機は、今や世界中に輸出されている。アジアや南米など、〝串料理〟がある国からの引き合いが絶えない。ただ、ここまでの道のりは決して平たんではなかった。創業者の小嶋實社長(80
)を襲った苦難は数え切れない。借金、粗悪品のレッテル、技術流出―。それでも、決して諦めない粘り強い経営が、オンリーワン企業を生んだ。(千葉 龍太)
■借金2千万円
小嶋社長の出発点は、幾度となく陥った「人間不信」。
都内の大学の工学部を卒業後、ベアリングメーカーを経て知人らと自動化設備の製造会社を川崎市内で設立。技術担当として働いた。
数年は順調だったが、実印を預けていた当時の社長による使い込みが発覚し、連帯保証人として2千万円の個人負債を背負う羽目に。1977年のことだ。
莫大な借金を抱えながら、会社をたたもうと、深夜まで残務整理に追われた小嶋社長。
やりきれない思いを抱えながら、仕事が終わると、毎晩のように会社近くの居酒屋で酒を飲んだ。
ツケもたまっていた。
ある日、いつもの居酒屋に顔を出すと、店の主人から「もう出せる料理がないので閉店にする」と言われ、ちょっとした口論になった。
「焼き鳥は、串刺しの作業が大変なんだよ。自動で刺してくれる機械でも作ったらツケ代は相殺してやる」
店の主人からの言葉が、開発のきっかけになった。
残務整理の傍らで、自動串刺機の開発に没頭した。私生活も「これ以上落ちることはないと言っていいほど、最低でしたね」と振り返る。だからこそ、後がなかった。
開発試験で使う肉代が払えず、早朝から精肉店でアルバイトして給料代わりに肉の切り身をもらった。
さまざまな形の肉に串を刺すのは、手作業でも難しい。まして機械で固定して刺しても、肉と肉のすき間が均等にならない。小嶋社長は、試行錯誤の末、バラツキをなくすには肉を載せるトレーにヒントがあることに気づいた。土台部分の形状を工夫して解決策を編み出した。
■相手にされず
ようやく自動串刺機の本格販売に乗り出したのは、1980年代後半だった。
市場を見渡せば、すでに先行メーカーは数社あった。しかし、どの機械も、串を均一に刺すことができない。
「串刺機は使い物にならない」。売り込み先となる外食業界から、いつの間にかそんなレッテルを張られていた。
小嶋社長は開発した製品を自動車に積み、全国各地の居酒屋や飲食店を回るが、誰も聞く耳を持たなかった。車中での宿泊、睡眠時間3時間は日常茶飯事。そんな日々が続いていた。それでも諦める訳にはいかない。
85年には現在のコジマ技研を設立。自動串挿機の専業メーカーとして、勝負に出た。
■粘り腰が奏功
やがて〝粘り腰〟の営業が奏功し、ついに大手食品メーカーへの納入が決まった。
とはいえ、そんな矢先のことだ。提携関係にあった製造委託先と販売を任せていた2社が図面を勝手に持ち出し、類似品の販売を始めた。
本当に悔しかった。それでも、「真似をするなら真似すればいい。うちはそれ以上の機械を作ってやる」と自らを奮い立たせた。
以来、毎年のように新製品を出し続けた。1時間で1万本以上刺せる上位モデルも発売した。値引き交渉にも応じなかった。こうした姿勢が同業他社との差別化にもつながった。03年、競合メーカーが倒産したことで、事実上のオンリーワン企業になった。
■新製品は毎年
現在も1年に1回、新製品を出す姿勢は変わっていない。利用者の声を、翌年の新製品開発にすぐに反映させることもできるからだ。
海外へ輸出するようになってから、同じような製品を出す企業も後を絶たない。それでも「うちのような中小企業が特許論争をしても時間と労力を費やすばかりです。むしろ、真似する企業が出てくるほど、うちの製品も売れていると思っています」と前向きだ。
今年で80歳になった。それでも「昔から体は頑丈」という小嶋社長は、現在でも週2回ほど、スポーツジムに通い、趣味のマウンテンバイクも楽しむ。
〝人間不信〟からの出発―。数々の逆境をプラスにする人生を実践してきた小嶋社長。
「米国と南米、それにアジア、中東、欧州…。串刺機のニーズは世界中にあるんです。これからは、世界にもっと売っていきたい」と未来を見据えている。