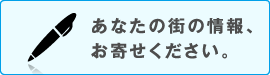相模原市南区上鶴間に社を構える千寿産業の岩崎正三会長(80)は、中学3年の時に新潟から上京。新聞配達で学費や食費を稼いだ。大学進学失敗も、映画配給会社で新た道を見つけた。その後、経理部長として現在の千寿産業の前進である大町田スポーツセンターの立ち上げに関わった。株主募集や従業員の面接、建設業者との打ち合わせと開業するまでは休む暇もなかった。社長になってからは、めまぐるしい時代のなか、お客のニーズを探り、「今よりも一歩先行く経営を」とさまざま企画や事業を行った。こうした岩崎会長の経営が今の千寿産業の礎になっている。(船木 正尋)
■14歳で上京
千寿産業は、婚礼や宴会のラポール千寿閣や町田ボウルを運営する。従業員数50人。
岩崎会長は新潟・妙高市出身。5人兄弟の末っ子で、小学6年生の時に終戦を迎えた。将来の夢は、小学校の先生になることだった。中学2年生まで新潟に住んでいたが、恩師に勧められ、中学3年生の春に上京した。14歳の時だった。岩崎会長は当時を振り返る。
「中学の先生に『お前は末っ子だから田畑はもらえない。東京へ行ってみたらどうだ』とアドバイスを受けまして、上京を決めました」
東京・代々木で新聞販売店を経営する叔父の世話になることになった。そこから学校にも通った。
「住む場所と食べることには困らなかったですが、食費と学費は叔父のところで稼ぎました。朝が早くて大変でしたね」
午前4時半には起床して朝刊を配達。帰っても夕刊があった。
勉強時間も考えると、睡眠はほとんどなかった。岩崎会長は「勉強と労働の両立はつらかったです。授業中に寝てしまうこともありましたが、先生が気を使ってくれました」と語る。
こうして高校卒業後は、念願の教師を目指すため、希望の大学を受験するが失敗。結局、新たな道を探すことになった。
■新たな道へ
外国映画の配給会社「三映社」に入社することになった。かつて上京を勧めてくれた恩師の紹介だった。
当時、そこで社長を務めていたのが、ラポール千寿閣の初代社長の大津治郎吉氏。岩崎会長にとって将来を決める出会いだった。
三映社では多くの外国映画の輸入に携わった。なかでも、ナチスの虐殺を描いたドキュメンタリー「13階段への道」を日本で上映するためには骨を折ったという。
「税関とのやりとりが大変でしたね。残虐性がありすぎると言われ、編集を何度も重ねました。1年間交渉し、やっと上映にこぎつけました」と岩崎社長。封切の時は、上映場所である丸の内松竹は長蛇の列だったという。それを見て、これまでの苦労は決して無駄ではなかったと、感動を覚えた。
■開業に奔走
1960年代、映画業界の繁栄は、テレビの普及によって終わりを告げることになる。三映社では、初代社長の大津氏が、テレビの普及を予見して映画業界から撤退することになった。地元である町田、相模原はレジャーと婚礼施設がなかったため、それをつくって運営しようと、180度の業態転換を図った。結局、これが千寿閣の始まりとなる。
64年、東京五輪の年に「大町田スポーツセンター」を設立した。開業の準備期間には1年を要した。地元の有志から協力を得るために株主募集をしたり、建設の打ち合わせなど、岩崎会長は奔走した。
経営に携わるには数字に明るくなければということで、開業までの1年間、夜間の経理学校にも通った。
65年には婚礼を行う千寿閣と町田ボウルが開業。岩崎会長は、ボウリング場の運営を任された。ボウリングが大ブームとなっていたこともあり、地域最大級の36レーンを誇った。
ブームが去り、スポーツジムやサウナに改築した。エリア初のスポーツジムになった。時代の流れを読み、先取りした経営を実践した。岩崎会長は「飛躍的に10、20歩先を行く必要はない。今よりも一歩先を行く経営をしていかなければならない」と説明する。
■絆を大切に
新生ラポール千寿閣として生まれ変わった85年。岩崎会長は第5代社長に就任した。
社長としてはじめに取り組んだのが、ホテル部門の強化だった。遠方から来るお客を逃さないために宿泊施設を設けた。ガーデンチャペルも新設した。
岩崎会長は「当時は、どこの式場にもホテルの中に小さいチャペルがあった。だからうちは、ホテルの外にチャペル作った」と説明する。
宿泊施設とガーデンチャペルの充実で、前年の倍以上のカップルが挙式した。
また、90年代には、ハワイ・オワフ島のヨットハーバーを一望できるコンドミニアム購入。挙式を済ませたカップルに無料で貸し出した。ホノルル空港からリムジンで送迎までしてくれるという演出まで行った。この企画も大ヒットした。
岩崎会長は強調する。「お客様との絆作りがこの仕事で一番重要だと思う。だからこそ、『絆』という意味があるラポールを付けた」と。
絆を絶やすことなく、今でも玄関で出迎える岩崎会長。おもてなしの心こそが地域最大級のホテルとしての実績と信頼を揺るぎないものにしているのだ。(2014年1月20日号掲載)